商標登録の区分とは? 登録の流れや弁理士に依頼するメリットを解説

ビジネスを展開する上で、自社の商品名やサービス名を守ることは非常に重要です。そのために行うのが「商標登録」です。商標登録は自社のブランドを法的に保護し、模倣や不正使用から守る手段として多くの企業や個人事業主が利用しています。
しかし、商標登録を行う際には「区分」という概念が欠かせません。この「区分」を正しく理解していないと、商標が想定通りに保護されなかったり、追加費用が発生したりする可能性があります。
本記事では、商標登録の基本的な概要から、「区分」とは何か、登録の流れ、そして弁理士に依頼するメリットについて、わかりやすく解説していきます。
商標登録とは?―ブランドを守るための法的手段
「商標」とは、商品やサービスに付けられる名称、ロゴ、図形、記号、色彩、音などを指します。商標登録をすることで、これらの要素が商標権として認められ、他者が勝手に使うことを法律で防ぐことができます。
例えば、「ABCカフェ」という名前でカフェを経営していて、同じ地域に「ABCコーヒー」という類似の名前の店舗ができた場合、商標登録をしていれば差し止め請求や損害賠償を請求できます。
商標権は、登録をして初めて法的に効力を持つ「登録主義」であるため、他人に先に登録されてしまうと自社で使っていたとしても権利を主張できないケースもあるのです。
商標の「区分」とは?―分類により決まる保護範囲
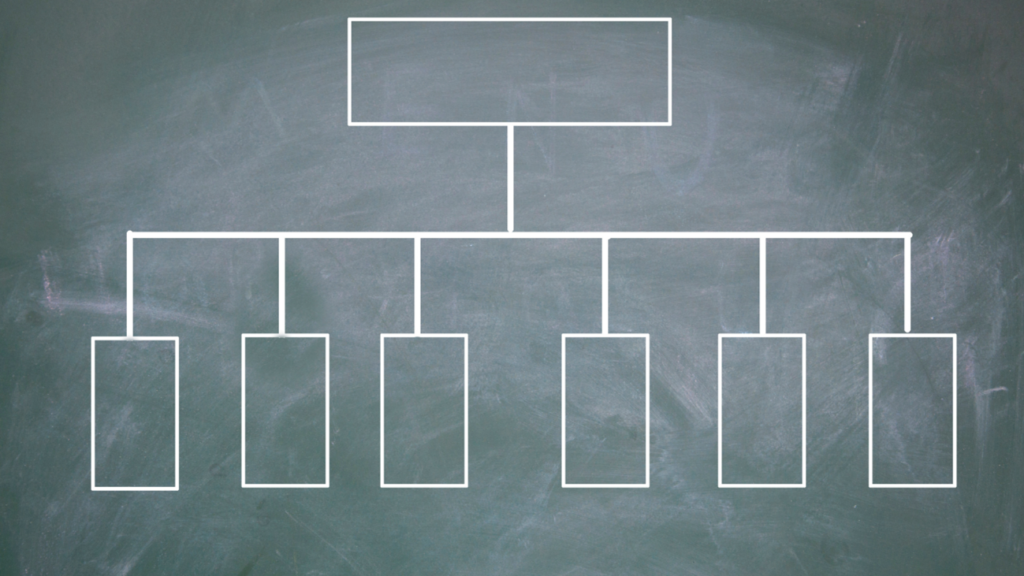
区分とは?
商標を登録する際には、何に対してその商標を使うのかを明確にする必要があります。たとえば同じ「SORA」という商標でも、飲料に使うのか、アパレルに使うのか、ITサービスに使うのかで商標の保護範囲は変わってきます。
この使用範囲を定める分類が「区分(分類)」です。日本では世界的な分類ルールである「ニース国際分類」に基づき、商品・サービスが第1類から第45類までの区分に分けられています。
区分の例
- 第9類:コンピュータソフトウェア、スマートフォン、電子機器など
- 第25類:衣類、靴、帽子など
- 第35類:広告業、事務処理代行、ECサイト運営などのビジネス支援サービス
- 第43類:飲食店、宿泊施設など
同じ名称の商標でも登録する区分が異なれば、それぞれ別の商標として登録することが可能です。つまり、「SORA」という名前が第9類と第43類でそれぞれ別の会社に登録されることもあるということになります。
区分の選び方
どの区分に登録すればよいかは、自社のビジネス内容と今後の展開を見据えて判断する必要があります。たとえば、飲食店を経営している場合は第43類に加えて、関連グッズを販売する予定があるなら第25類や第30類(食品)も検討対象になります。
なお、商標出願は区分ごとに費用がかかりますので、闇雲に多くの区分を指定すると無駄な出費になる可能性もあります。
商標登録の「45類」すべてを解説!―適切な区分選定のために
商標登録では、「何の商品やサービスに対してその商標を使うのか」を明確にするため、国際分類(ニース分類)に基づいた45の「区分」を指定します。第1類~第34類は「商品(モノ)」に関する分類、第35類~第45類は「役務(サービス)」に関する分類です。
以下に、全45区分を一覧で解説します。
【商品(第1類〜第34類)】
| 類番号 | 内容 |
| 第1類 | 化学品、工業用薬品、農業・林業用の化学製品など |
| 第2類 | 塗料、顔料、インク、染料などの着色料類 |
| 第3類 | 化粧品、洗剤、香水、歯磨きなどの衛生用品 |
| 第4類 | 工業用油脂、潤滑油、燃料(ガソリン・薪など) |
| 第5類 | 医薬品、医療用品、健康補助食品、防虫剤など |
| 第6類 | 金属製品(建築用、機械部品など) |
| 第7類 | 各種機械、エンジン、ロボット、産業機器 |
| 第8類 | 手工具、刃物類、電動工具、台所用刃物など |
| 第9類 | コンピュータ、スマートフォン、家電、電子機器全般 |
| 第10類 | 医療用機器、義肢、手術器具など |
| 第11類 | 照明器具、加熱・冷却機器、給湯器など |
| 第12類 | 自動車、バイク、自転車、部品など |
| 第13類 | 火薬、花火、武器、銃器など |
| 第14類 | 貴金属、宝石、時計、アクセサリー類 |
| 第15類 | 楽器、楽器部品 |
| 第16類 | 印刷物、書籍、文房具、紙類、写真など |
| 第17類 | ゴム、プラスチック、絶縁体などの加工材料 |
| 第18類 | カバン、財布、革製品、傘など |
| 第19類 | 建築資材(木材、石材、セメント等) |
| 第20類 | 家具、プラスチック製品、寝具、装飾品など |
| 第21類 | 台所用品、家庭用容器、掃除道具など |
| 第22類 | ロープ、テント、帆、ネット類など |
| 第23類 | 糸(織物用・編物用など) |
| 第24類 | 織物、タオル、布製品全般 |
| 第25類 | 衣類、靴、帽子 |
| 第26類 | 裁縫用品(ボタン・ファスナー等)、装飾品 |
| 第27類 | カーペット、マット、壁紙などの敷物類 |
| 第28類 | 玩具、運動用具、遊園地用品など |
| 第29類 | 食品(肉・魚・乳製品・加工食品など) |
| 第30類 | 調味料、菓子、パン、穀類加工品など |
| 第31類 | 生鮮食品(果物・野菜・穀物・家畜・魚介など) |
| 第32類 | 飲料(ノンアルコール)、ミネラルウォーター、ジュースなど |
| 第33類 | アルコール飲料(ビール・ワイン・日本酒・焼酎など) |
| 第34類 | タバコ、喫煙用具、電子タバコなど |
【役務(サービス/第35類〜第45類)】
| 類番号 | 内容 |
| 第35類 | 広告、販売代行、マーケティング、EC運営などのビジネス支援全般 |
| 第36類 | 保険、金融、不動産、投資など |
| 第37類 | 建設、修理、メンテナンス、リフォームなど |
| 第38類 | 通信、インターネット、電話、放送関連サービス |
| 第39類 | 輸送、配達、旅行代理業、物流など |
| 第40類 | 加工サービス(衣類印刷、食品加工、金属加工など) |
| 第41類 | 教育、研修、娯楽、イベント開催、スポーツ関連 |
| 第42類 | ITサービス、ソフトウェア開発、科学技術関連、クラウド提供など |
| 第43類 | 飲食店、ホテル、宿泊、ケータリングなど |
| 第44類 | 医療、美容、農業・園芸・動物ケアなど |
| 第45類 | 法律相談、警備、婚活、占い、人材紹介などの個人向けサービス全般 |
区分の誤りが致命的になることも…
たとえば、カフェ運営者が第43類(飲食業)だけを指定して商標登録した場合でも、店名を付けたオリジナルTシャツを販売するなら第25類(衣類)を追加する必要があります。登録していない区分では、商標権の保護が及ばず、他人に真似されても対処できません。
そのため、自社の事業内容・展開予定・ブランディング戦略を踏まえ、適切な区分を選ぶことが極めて重要です。
弁理士に相談すれば、必要最小限の区分で最大限の権利保護を得るためのアドバイスを受けられます。
商標登録の流れと費用
商標登録は、以下のような流れで進められます。
- 商標調査:既に登録されている商標と同一・類似のものがないかを確認
- 出願書類の作成と提出:必要事項(商標、区分、出願人情報など)を記載
- 方式審査・実体審査:特許庁による審査が行われ、問題がなければ登録査定
- 登録料の納付:審査に通過した後、登録料を支払って正式に登録される
- 商標権の発生:登録が完了すると商標権が発生し、10年間の保護が得られる(更新可能)
費用の目安
商標登録にかかる主な費用は以下のとおりです(1区分あたり)。
| 費用項目 | 金額(概算) |
| 出願料 | 約12,000円 |
| 登録料(10年分) | 約32,900円 |
| 弁理士報酬(任意) | 約50,000~100,000円以上(1区分) |
※区分が増えるごとに費用は加算されていきます。
弁理士とは?商標登録をサポートする知財の専門家

「弁理士(べんりし)」は、特許・商標・意匠などの知的財産権に関する手続きや相談を行う国家資格の専門家です。特許庁への出願手続きの代理ができるほか、拒絶理由通知への対応や無効審判などにも対応できます。
商標登録は一見シンプルに見えますが、実際には商標の選定や区分の指定、先行登録との比較調査など、専門知識が必要な場面が多くあります。これらを適切に判断するのが弁理士の役割です。
商標登録を弁理士に依頼するメリット
1. 的確な区分の選定
商標の使用目的に応じて、無駄なく・漏れなく区分を選定してくれます。将来的なビジネス拡張も見据えて、必要な区分を提案してくれるのも弁理士の強みです。
2. 先行調査の精度が高い
素人が行う商標調査では見落としがちですが、弁理士であれば類似商標の判定や特許庁の審査基準を踏まえて、登録可能性を事前にしっかり判断してくれます。
3. 拒絶理由通知にも対応できる
万が一、審査で「拒絶理由通知」が届いた場合、弁理士は法的根拠に基づいて意見書や補正書を作成し、登録に向けた交渉を行ってくれます。これにより、登録成功率が大きく向上します。
4. 時間と手間を大幅に削減
商標登録には専門的な書類作成や調査が必要であり、ビジネスオーナーが独自に行うのは負担が大きいです。弁理士に依頼することで、時間と手間を省き、安心して任せることができます。
商標登録では「区分」の選定が鍵!プロに相談を
商標登録において、「区分」の正しい選定は、商標の保護範囲を左右する重要な要素です。登録費用にも直結するため、過不足なく設定することが求められます。
弁理士に相談すれば、専門的な視点から商標の調査・出願・審査対応まで一貫してサポートを受けられるため、ミスなくスムーズな登録が実現できます。
ブランドを守る第一歩として、ぜひ弁理士の力を活用しながら、適切な区分で商標登録を進めていきましょう。
当事務所では商標登録に関するご相談も受け付けています。オンラインでも対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
お気軽にお問合せください。
◉ 弊所もしくはご自宅や会社にお伺いしてお打ち合わせいたします。ご希望をお聞かせください。
◉ パソコン画面を共有し資料を見ながらのオンラインお打ち合わせも可能です
◉ 電話/メールもご利用いただけます



